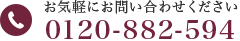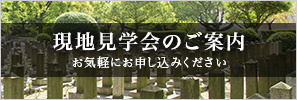供養の種類
供養に様々な種類が存在することを皆さんはご存知でしょうか。
そもそも供養とは「供養資養(くきゅうしよう)」の略で、「供給」はお給仕、「資養」は元手という意味をもちます。つまり、仏様にお給仕をすることが、生きている我々の心の成長(元手)になるという意味です。各宗派ごとの供養に対する捉え方や種類、在り方を正しく理解することは大切なことです。こちらでは、様々な供養の種類や決まりごとをご紹介いたします。
供養の種類
- 二種供養
- 香華(仏前に供えるお香とお花)・飲食物などの財物を供養する利供養と、教義に沿って修行を行い衆生を利益する法供養の2種類を指します。
- 三種供養
- 讃嘆恭敬(さんだんくぎょう)を行い先祖を偲ぶ心を養う敬供養、香華・飲食物を供える利供養、仏法を受けとめて修行する行供養の3種類を指します。
- 四事供養
- 飲食、衣服、臥具、湯薬の供養を指します。
- 密教の五供養
- 塗香、華、焼香、飲食、灯明の供養を指します。
- 六種供養
- 水、塗香(ずこう)、華、焼香、飲食、灯明の供養を指します。
- 十種供養
- 華、香、瓔珞(ようらく)、末香、塗香、焼香、幢幡(どうばん)、衣服、妓楽、合掌の供養を指します。
- 三密供養
- 密教での身・口・心の行を指します。
- 追善供養
- 死者の冥福を目的に行う供養です。
- 施餓鬼供養
- 六道(天・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄)の一つ餓鬼の境遇に墜ちた亡者は口にしようとした食べ物が忽ち炎と化して、何一つ食べることが出来ません。そんな餓鬼に食べ物を施し、その苦しみから少しでも脱することが出来るようにする行事。(浄土真宗にはありません)
- 彼岸供養
- お彼岸とは中日を挟んで前後三日間の合わせて1週間の行事です。お中日とは太陽が真西に沈む春分・秋分の日です。昔から西には西方浄土といって仏の世界があり極楽とされています。極楽に生まれた(往生)先祖を偲び、今日ある自分を育んでくれた先祖に感謝し、自分も死なば極楽浄土に行きたいと決意を新たにする実践週間です。
- 開眼供養
- 建立された墓石、仏像、位牌、仏画等に対する供養です。
- 入仏供養
- 仏像を新たに、仏壇や寺院に迎える供養です。
- 開題供養・経供養
- 経文を書写して供養することです。
宗派による違い
仏教の世界では、各宗派の教義によって供養の方法に独自の決まりがあります。
関連した用語の呼び名ひとつとっても宗派によって一様ではありません。たとえば「戒名」という言葉。浄土真宗や日蓮宗では「法名」と呼ばれています。こちらでは、各宗派による違いをご紹介します。
- 浄土宗
- 浄土宗では供養の際、在俗戒名に「誉」を付けます。浄土宗系の「時宗」では、男性に「阿」、女性に「弌」を付けることもあります。
墓石には、戒名の上に梵字のキリーク(阿弥陀如来を表す文字)を付けたり、戒名の代わりに「南無阿弥陀佛」と彫ることもあります。 - 浄土真宗
- 浄土真宗では供養の際、院号・道号・位号、位牌がありません。
授戒(仏門に入る者に師僧が戒律を授けること)がないため、戒名ではなく法名といいます。
法名の前に男性は「釈」を、女性は「釈尼」を付けます。(仏光寺派や近年男女平等の考えから尼を付けない場合やもある)また死後の霊魂を認めませんので、追善供養や卒塔婆はなく、お盆などの習慣も他宗と異なった解釈をします。墓石には「南無阿弥陀佛」「倶会一処」と彫ることが多く、梵字も使いません。 - 天台宗
- 戒名は、院号・道号・戒名・位号からなり、天台宗の特徴を示す特別なものはありません。
墓石は、戒名を正面の竿石に彫る場合は、梵字の「ア」(大日如来を表す文字)、または「キリーク」(阿弥陀如来を表す文字)を上につける場合が多いようです。 - 禅宗(臨済宗・曹洞宗)
- 戒名は基本的に天台宗と同じで、特徴を示す特別なものはありません。
墓石には、上部に「円相」という円が書かれることがあります。お題目の「南無釈迦牟尼佛」と書く場合もあります。 - 真言宗
- 真言宗では供養の際、戒名の前に「ア」(大日如来を表す文字)を付けることがあります。
墓石は、戒名の上にも梵字の「ア」を付けます。 - 日蓮宗
- 日蓮宗では供養の際、戒名といわず法号といいます。女性に「妙」の文字を付けるのが特徴です。
墓石には、独自のヒゲ文字で「南無妙法蓮華経」の文字を書くことが多く、特にこうした文字をヒゲ題目と呼びます。
また竿石に、法号や「○○家之墓」を彫る場合には、上部に「妙法」の文字を入れることがあります。
当霊園にご相談ください
寺院が苑内にあるので、お墓参りの際に、供養を行うことができます。
霊園にお越しの際は、お気軽にご相談ください。